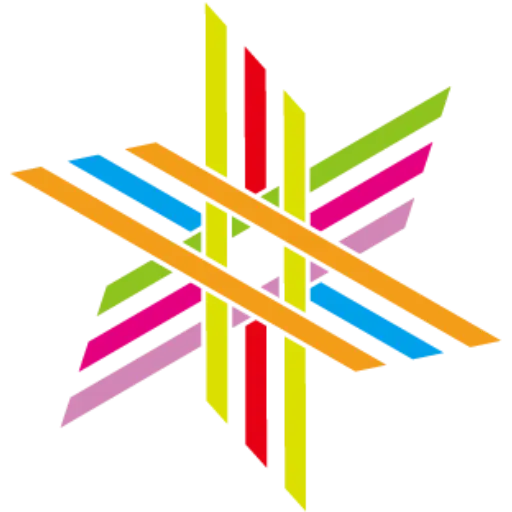事例紹介
case
top page - case
staff
経験豊富なスタッフが
サポートいたします。
安心できる未来を共に築く―
お客様一人ひとりの「想い」を大切にしながら、
私たちは真心を込めて寄り添います。
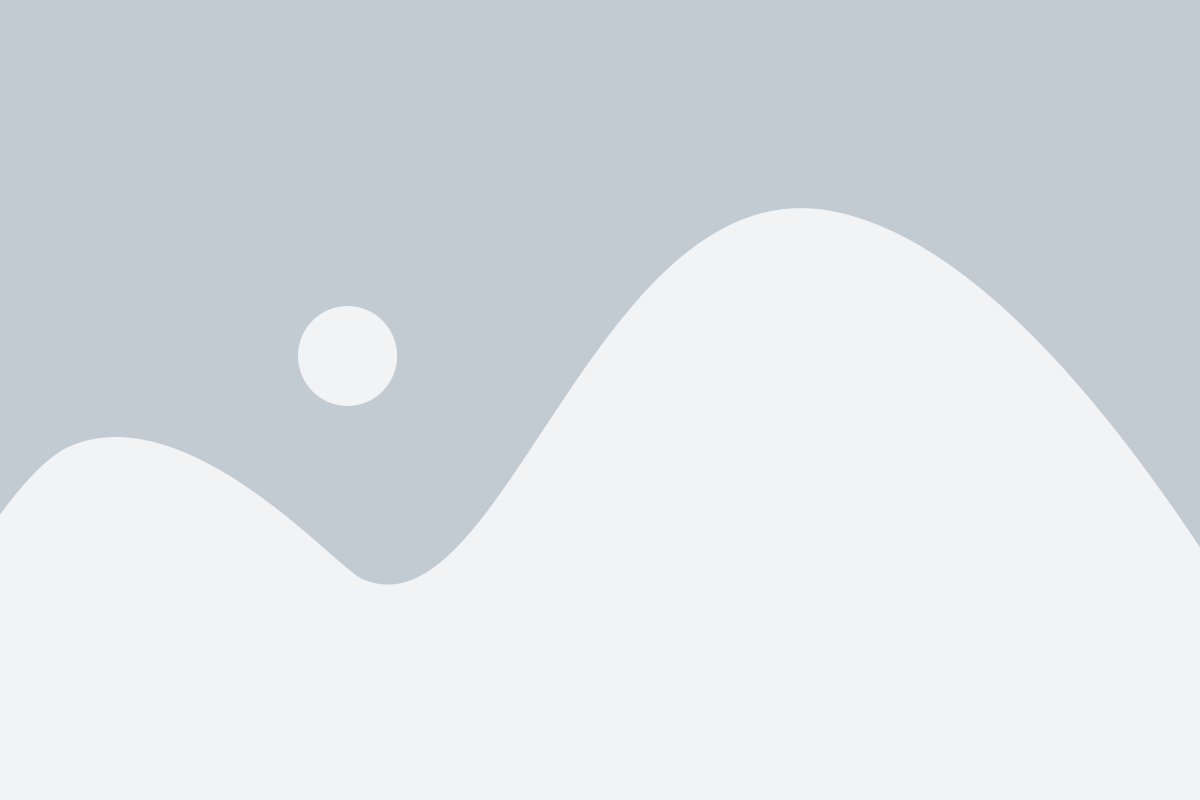
case
各種保険についての
事例をご紹介します
初めての
ご相談でも
ご安心ください
ご相談内容
30代の共働き世帯・お子さま1人。持ち家にお住まいです。住宅ローンは団信加入済み。保険は終身300万円と医療のみで、就業不能の備えは未加入。自動車保険は毎年更新継続で、特約の見直し歴はありません。万一の際に教育費と生活費をどこまで賄えるか不透明で、今の保険が、果たして自分たちに合っているかを相談したい漠然と不安な形から脱却して妥当性のある保険にしたいご意向でした。
家計の年間支出・教育費・葬祭費・遺族年金等から必要保障額を試算したところ、お子さま独立までの死亡保障は概ね2,000万円前後が目安となりました。現状の死亡保障は終身300万円のみで不足約1,700万円、就業不能の備えは未加入。さらに医療特約には入院・通院・がんの重複が見られ、費用対効果が下がっていました。自動車保険は年齢条件・運転者限定・走行距離区分が未最適化、特約の重複も確認。保険料総額は月約11,000円で、家計を圧迫している費用負担ではなかったが、保障の内容的にご家族がおられる観点からも整理の余地がある状況でした。
不足分を中心に再設計し、収入保障(月10万円・ご主人60歳まで)+定期500万円(20年)で万が一時の生活費をカバー。しかもその収入保障に就労不能の際も、カバーできる内容にすることにより安心度を高めました。 医療は特約を解消し、ご主人が心配されている、がん重症化リスクに重点を置いた一時金タイプへ変更しました。 自動車保険は年齢条件・運転者限定・対物超過修理費用等の見直しと不要特約の削除を実施。 総保険料は月約9,000円へ抑制し、家計負担率の適正化を図りました。 あわせて、進学・昇給・転居などの節目での点検ルールと解約返戻金・更新時期の管理台帳を共有し、継続的に過不足を整える方針を明確化しました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。
case
資産運用についての
事例をご紹介します
初めての
ご相談でも
ご安心ください
ご相談内容
40代のご夫婦。手元資金は普通預金が中心で、投資経験はごく少なめ。毎月、積立に回せる余力は数万円を想定されています。教育費と老後資金の資金分けが未整理。価格変動時の向き合い方や手数料の基準が不明確で、無理なく続けられる仕組みづくりを希望されました。
40代のご夫婦で、預貯金約1,000万円が普通預金に偏在。教育費と老後資金を計画的に準備したい一方、投資経験はほぼなしで、価格変動や下落時の対応に不安をお持ちでした。資金は目的別の仕分けが未実施でインフレ耐性が弱い構成。過去に高コスト商品の提案を受けたご経験から、手数料の基準や商品比較の軸が曖昧で、毎月の積立可能額は8万円程度と把握されていましたが、配分方針は未定でした。
目的・期間・リスク許容度を整理し、資金を短期・中期・長期に区分。短期は生活防衛資金として6か月分を流動性重視で確保。中期(〜10年)は教育費として月3万円を債券比率高め・低コスト投信で積立。長期(10年以上)は老後資金として月5万円を世界分散インデックス中心(信託報酬年0.1%台)で開始しました。優先的に非課税制度の活用枠を配分し、年1回のリバランスと手数料上限の運用基準を設定。積立日は給与日の直後に固定し、増額・一時入金の判断基準も共有。これにより、“続けられる金額で続けられる仕組み”へ移行しました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。
case
ライフプランについての
事例をご紹介します
初めての
ご相談でも
ご安心ください
ご相談内容
30代前半のご夫婦・お子さま1人。数年内の住宅購入を検討中。返済比率の上限設定は未確定で、教育費の試算は概算段階。通信・サブスク等の固定費もそのままになっています。購入後の家計バランスと貯蓄ペースの維持が心配。保険や固定費の重複を整理し、見直しの優先順位を明確にしたいご希望でした。
30代前半のご夫婦・お子さま1人で、3,500万円前後の住宅購入を検討。教育費との両立可否や返済比率、貯蓄ペースへの影響をご心配でした。作成したキャッシュフローでは、返済比率の上限が未設定で、教育費は概算のまま。保険・積立・通信等の固定費に重複があり、将来の資金ピーク(高校・大学進学期)にキャッシュ不足の可能性が示唆されました。金利変動や二人目のご予定などのシナリオ管理も未整備でした
キャッシュフローを65歳まで作成し、住宅は手取りの25%以内を上限に返済計画を設計。頭金300万円・ボーナス返済なし・長期固定を基準に諸費用を含めて比較しました。教育費は進学時期に合わせ月2万円の積立を開始し、ピーク時不足はボーナスの一部充当で対応。団信前提で死亡保障を調整し、就業不能の備えを追加。通信・サブスク等の見直しで月約15,000円の余剰を創出し積立へ振替。住宅維持費(修繕・更新)用の積立も月額で設定。金利動向・家族構成の変化・昇給を年1回の見直し項目としてルール化し、将来の資金ショックに備える体制を整えました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。
case
相続・贈与についての
事例をご紹介します
初めての
ご相談でも
ご安心ください
ご相談内容
相続人はお母さまとお子さま二人。資産は自宅と預貯金が中心で、お母さまは自宅に住み続けたいご意向でした。手続きの順序や必要書類・期限の見通しが持てず、税負担を抑えつつ将来の売却も見据えた分け方の整理をご希望でした。
遺産の概算は約5,200万円で、基礎控除4,800万円をわずかに超過し、相続税は少額発生見込みでした。自宅を共有相続とすると、将来売却時にお子さまが居住用の特別控除を使えない可能性があり、譲渡所得税の負担増が懸念されました。戸籍・評価証明・金融機関の手続きは着手途中で、申告期限までの工程表や必要書類一覧は未整備の状況でした。
分割方針は、お母さまが自宅を単独で相続し、お子さま二人には代償金で公平を図る設計をご提案しました。居住継続を前提に小規模宅地等の特例の適用可否を確認し、預貯金は遺産分割協議書に基づき按分。相続登記・金融機関手続き・申告のタイムラインを作成し、必要書類と費用目安を共有しました。さらに将来売却に備え、譲渡時の特別控除や保管すべき証憑の管理ルールも整理。司法書士・税理士と連携し、手戻りを防ぎつつ進行した結果、税負担と事務負担の双方を抑え、期限内完了の見通しが立ちました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。
case
金銭教育セミナーの
事例をご紹介します
初めての
ご相談でも
ご安心ください
ご相談内容
小学校PTAさま(高学年対象)からのご依頼。庭での金銭教育は話題になりにくく、キャッシュレスの概念理解に差がある状況。開催にあたり、時間配分・人数・設備面の条件整理が必要でした。子どもが主体的に学べる内容と、家庭で継続できる仕組みを求めておられ、運営の負担を抑えつつ具体的な進め方を知りたいご要望でした。
小学校PTAさまより、高学年向けの金銭教育について出前授業のご依頼。おこづかいの使い方・貯め方・キャッシュレスの理解を楽しく学びたい一方、家庭での会話化が難しく、使いすぎや“ねだり”による衝突が課題でした。授業時間・人数・会場設備など運営面の不安もあり、具体的な進め方のイメージを求めておられました。
45分×2コマで構成し、「3つの箱」(使う・貯める・分け合う)の配分ワーク、欲しい物の優先順位づけ、セール表示の読み解きを体験形式で実施。家庭用ワークシートと振り返り用チェック表を配布し、月1回の家庭学習を促す仕組みを整えました。教員向け進行台本・投影資料も提供し、準備負担を軽減。事後アンケートでは「おこづかいのルールを家族で決めた」「買い物前に相談する習慣ができた」等の声を多数いただき、次年度以降の継続開催に向けた評価基準も共有しました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。
case
士業紹介サポートの
事例をご紹介します
初めての
ご相談でも
ご安心ください
ご相談内容
相続手続きを進めるご家族さま。相続登記・税務・遺留分の論点が並行しており、必要書類の収集は途中。関与先の選定は未了です。の専門家に何を依頼するか、費用・スケジュール・連絡窓口を一本化したいニーズ。手戻りなく進める進行管理を求めていらっしゃいました。
相続に伴う不動産の名義変更・預貯金の手続きに加え、遺留分への不安があり、どの専門家に何を依頼すべきか判断がつかない状況でした。登記・税務・遺留分の論点が混在し、優先順位とスケジュールが不明確。費用感・必要書類の把握が難しく、窓口が複数に分かれることで手戻りの懸念がありました。
論点を整理のうえ、司法書士(相続登記)/税理士(相続税申告・評価)/弁護士(遺留分)の三者連携体制を構築。当社が一次窓口となり、必要書類・期限・費用目安をまとめた進行表を共有しました。初回面談で役割分担・連絡経路・意思決定フローを確定し、問い合わせも一本化。これにより、手続きの停滞を避けつつ、期間・コストの見通しが明確になり、申請・申告までの道筋が整いました。
※金額・商品構成は一例です。実際の設計は年収・ご資産・公的保障・既契約内容等により異なります。